ソフトウェア調整
ハードウェアの調整が済んだら、ソフトウェア調整を行います。
ソフトウェア調整は、OSレベルの設定とアプリケーションレベルの設定がありますが、
ここでは、OSレベルの設定について、設定の方向性と簡単な説明に留めます。
詳しい調整は、自分の使っているシステムと作品に合わせてカスタマイズが必要に
なりますので、責任者と打ち合わせの上行ってください。
- マッキントシュの場合
マッキントシュの場合は、ビデオアダプタの出力に対してOS側からの調整が行えます。
「カラーシンク機能拡張」を ON の状態で OS を立ち上げると調節機能が使用できます。
ハードウェア調整の前に OFF にした 「カラーシンク機能拡張」を有効にして、
OS を再起動して下さい。
再起動後は、OS付属の「モニタ&サウンド」コントロールパネルから、
「カラー調整アシスタント」を呼び出して最終的なソフトウェア調整が行えます。
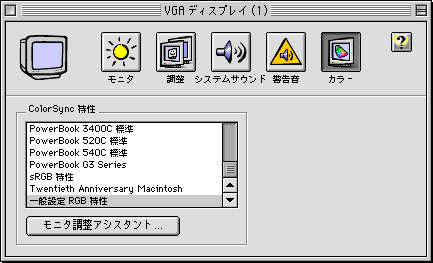 「モニタ&サウンド」コントロールパネル
「モニタ&サウンド」コントロールパネル
 カラー調整アシスタント
また、adobe社の製品がインストールされている場合は、「カラー調整アシスタント」
の代わりに、「アドビ ガンマ ユーティリティ」を使用することもできます。
カラー調整アシスタント
また、adobe社の製品がインストールされている場合は、「カラー調整アシスタント」
の代わりに、「アドビ ガンマ ユーティリティ」を使用することもできます。
注意事項
必ず、現在使用中の OS の「カラーシンク」機能に対応した
ユーティリティーを使うようにして下さい。
(旧来の「KNOLL」ガンマコントロールは、現在のカラーシンクに対応していません)
カラーマネジメントの二重管理だけは必ず回避して下さい。
|
- ウィンドウズ(系)の場合
Wiindows (系)の システムの場合
ソフトウェア調整が可能な場合があります。
Wiindows は 基本的にOS側で画面表示には関与しません。
したがって、ソフトウェア調整が可能な場合とは、
ビデオカード(ビデオアダプタ)のメーカーが、
「ソフトウェア調節可能なビデオドライバを提供している場合」
のみに、限られます。
現在のビデオ表示ドライバが、ソフトウェア調節機能を持っていない場合でも、
ドライバをアップデートすることで対応できる場合があります。
確認した限りでは、RAGE-128 i810 MAG-G400 PARMEDIA PARMEDIA2
などのドライバは、調整機能を持っている様です。
|
調整機能の使用方法は、メーカー毎にまちまちですが、
大きく別けて二つのパターンがあるようです。
一つは、デスクトップのプロパティで調整できる場合で、図のようにプロパティシートに調整機能が拡張されます。
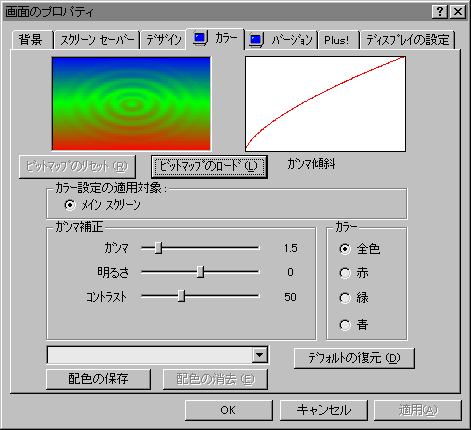 [図: インテル i810 ドライバの例]
もう一つは、コントロールパネルから調節ユーティリティーを呼び出す形で
比較的古いビデオアダプタのドライバに多いようです。
[図: インテル i810 ドライバの例]
もう一つは、コントロールパネルから調節ユーティリティーを呼び出す形で
比較的古いビデオアダプタのドライバに多いようです。
- その他のシステムの場合
多岐にわたるため、ここでの説明は行いません。
それぞれのシステムのマニュアルにしたがって調整方法を確認して下さい。
グラフィックワークステーションとして使用するシステムならば、
なんらかの形で調整機能は、提供されていると思います。(思いたい)
調整に際して
ソフトウェア調節が可能な場合は、これらのコントロールユーティリティを使用して、
システムの表示状態を、目標の作業プロファイルにできる限り近づくように調整します。
調節可能な内容、および範囲はそれぞれの状況で異なるため、
ここでは、細かい記述は避けますが、基本的には、モニタ側のハードウェア調整で
カバーしきれない
「ガンマ調整」
を行うことになります。
ガンマ目視チャートを表示して、ユーティリティーのガンマ調節を行い
「目標ガンマ」に近似するポイントを出して下さい。
さらに、測定器が使える状況であれば、測定を行って記録して下さい。
また、明るさ、コントラスト、画面位置の調整など ハードウェア調整で処理しきれ
なかった部分を、ユーティリティーで補える場合があります。
調整作業の際の注意点として、
「全体の見た目が充足しているときは、数値を合わせるためだけの追加調整は避ける」
という心がけを持って下さい。
測定数値は、あとからついてくるもので あくまで、見た目が優先です。
何度も経験を積んで、自分の目を鍛えて下さい。
荒っぽい解説ですみません。
ケースバイケースになる部分があまりに
多くて、具体的には書きにくくて・・・
kiyo
Nekomataya / Kiyo 2000
|
2000.07.07
|
モニタ調節-3
|

|






「モニタ&サウンド」コントロールパネル
カラー調整アシスタント また、adobe社の製品がインストールされている場合は、「カラー調整アシスタント」 の代わりに、「アドビ ガンマ ユーティリティ」を使用することもできます。
[図: インテル i810 ドライバの例] もう一つは、コントロールパネルから調節ユーティリティーを呼び出す形で 比較的古いビデオアダプタのドライバに多いようです。
